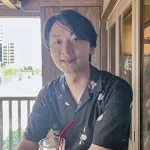博士課程学生が振り返る初めての国際誌論文執筆日記-投稿準備編

博士課程学生として活動している私が、2025年の論文投稿・目標誌へのアクセプト(採用)を目指して取り組んでいる過程を紹介します。研究の世界では、「論文を書く」というと完成形だけをイメージしがちですが、実際には長い準備期間があり、その過程で多くの学びがあります。私が初めての国際誌論文投稿に向けて準備を始めた2024年半ばから、現在に至るまでの記録をまとめました。この記事が、これから論文執筆に挑戦する方々の参考になれば幸いです。
2025年4月現在のステータス
現在、博士課程の学生で、初めての論文投稿に向けた準備を続けています。2025年に国際誌に論文投稿・目標誌へのアクセプトを目標としています。このおよそ一年間の活動を時系列で振り返ってみます。
| 2024年5月 研究結果の確認 | 6月 論文作成の承認とマテリアル・メソッドの着手 | 7月 理論モデルの構築 |
| 8月 追加実験の実施 | 9月 追加実験の実施 | 10月 追加実験の実施 |
| 11月 投稿先の選定と英語ドラフトの着手 | 12月 英語ドラフト第1版の完成 | 2025年1月 |
| 2月 評価フィードバックと追加検証 | 3月 英語ドラフト第2版の完成 | 4月 投稿目標 |
2024年5月:研究結果の確認
昨年5月にコアの実験結果が出ました。それまで実験を繰り返し、コードの改良を重ねてきた結果、研究の中核となる現象を確認することができました。この時点ではまだ論文化の準備はしていませんでした。
6月:論文作成の承認とマテリアル・メソッドの着手
指導教員とのミーティングで実験結果を共有し、論文作成へのGoサインをいただきました。これが論文プロセスにおける重要なスタートの節目となりました。
論文作成の方針について検討する中で、まずはMaterials and Methods(マテリアル・メソッド)セクションを日本語で記述することから始めました。自分の研究手法を体系的に整理するのに適した方法だという判断でした。
7月:理論モデルの構築
マテリアル・メソッドの日本語ドラフトが一定の形になりました。自分が作成したモデルを説明する数式による理論展開の記述は想像以上に難しく、形にすることで初めて理解が深まることもありました。
今は、Texを使って数式を書くのにAIが使えるので、数式作成に関してはかなり楽になっています。
8月〜10月:追加実験の実施
論文のドラフトを作成する中で、主張を裏付けるために必要な追加データや検証すべき仮説が明確になってきました。当初は「十分な結果が得られた」と考えていましたが、論文として主張を確立するにはさらなる証拠が必要でした。
この3ヶ月間は、追加実験のためのコード開発、実験実行、結果解析とまとめに集中しました。当初計画していなかった実験も含まれていて、この過程で研究の方向性がより精緻になっていくのを実感しました。
11月:投稿先の選定と英語ドラフトの着手
投稿先雑誌を選定しました。研究テーマに適合し、かつ自身のモチベーションを維持できる雑誌を指導教員と協議して決定しました。雑誌によって求められる論文構成や強調すべき要点が異なるため、この選定は重要なステップでした。
また、日本語でのドラフトがある程度完成し、英語ドラフト(バージョン1)の作成に着手しました。日本語ドラフトは、将来の博士論文作成にも活用できるよう、詳細に記録しておきました。
12月:英語ドラフト第一版の完成
昨年末に英語ドラフトのバージョン1が完成し、指導教員(共同著者)に提出しました。日本語から英語への変換は単なる翻訳ではなく、国際的な読者に向けた論理展開の再構築が求められるため、先生の添削が必要です。
2025年2月:評価フィードバックと追加検証
指導教員からの添削と、AIを活用した疑似査読による評価により、バージョン1の改善点が明確になりました。AIを疑似査読者として活用し、論文構成に対する批判的なフィードバックを得る方法は、客観的視点を取り入れる上で有効でした。
これらのフィードバックに基づき、追加実験を実施し、結果を体系化しました。図表も含めた内容の大幅な更新作業には、相応の時間が掛かりましたが、論文の質は確実に向上していきました。
特に、サブミット前にあらかじめAIに査読チェックしてもらえるようになったことは、研究体験でとても有効でした。アクセプト確率をブーストするためにも、AIに辛口でダメ出ししてもらい、批判に対する改善フィードバックも受けるのが大事だと感じました。
3月:英語ドラフト第二版の完成
英語ドラフトのバージョン2が完成し、投稿に向けた最終調整に入りました。この段階では、表現の精緻化や引用文献の確認など、細部にわたる調整が中心となりました。
4月:投稿目標
投稿を目標に、現在も最終調整を進めています。
投稿準備を通じて学んだこと
この一年間の活動で、さまざまな学びと気づきを得られました。
1. 論文執筆の承認からが本格的な研究の始まり
初期段階の結果が得られた時点では、論文を構成するストーリーはまだ完成していませんでした。私の場合、追加で複数の実験を実施し、結果を分析していく過程で、徐々に論文としての構成が確立されていきました。「結果が得られた」と認識した時点では、実際には研究プロセスの中間段階にすぎなかったことを実感しました。
2. 試行錯誤のプロセス
研究過程では、最終的に論文に採用されない分析や不要な機能開発も数多く作業しました。一見無駄に思えるこれらの作業も、研究の方向性を決定する上で重要な判断材料となりました。
最初の経験なので、無駄な作業が多かったと感じました。しかし次回、別の論文を書くときに、より効率的なプロセスを選べる直感が醸成されたようにも感じています。
3. 重要度の高い分析の優先順位付け
論理展開において核心となる重要な分析ほど、早期に実施することの重要性を学びました。後になって「この検証が必要だった」と気づくと、それまでの執筆作業の多くで再考が必要になってしまいます。
4. 図表の重要性
研究内容が適切に伝わり、可読性と情報量を兼ね備えた図表がなければ、論文の価値は十分に伝わりません。投稿準備において最も時間と労力を投入すべきは、図表の作成だと実感しました。研究の本質を視覚的に伝える図表の作成は困難ですが、それに見合う価値があります。私は何度も図を修正しました。
5. 効率化の課題
論文執筆の経験を積めば、自然と効率が向上すると考えていました。しかし、実際には各論文により求められる内容や焦点が異なるため、完全な効率化は容易ではないことを認識しました。
6. 実験の不確実性への対応
下記の参考文献はめっちゃ必読です。というか、ほぼすべての大事なことが書いてあります。
「実験は不確実性が高いため先に確定させる」という原則の重要性を実感しました。実験結果に依存して論文構成が決まるため、実験を後回しにすると修正作業が増大するリスクが高まります。早期に核となる実験結果を確定させることが、効率的な論文執筆の鍵となります。
研究の進め方 ランダムネスとの付き合い方について 佐藤竜馬 – Speaker Deck
初めての国際誌論文執筆は、想定以上に複雑かつ長期的なプロセスでしたが、その分だけ多くの学びを得られる貴重な経験となっています。まだ投稿前の段階ですが、これまでの準備を通じて研究者としての視点が徐々に形成されていると感じています。
次回は、投稿後のレビュープロセスについても共有できればと思います。投稿に向けて、引き続き準備を進めていきます。
BlueMemeの博士課程学生たちの活動は、ここリープリーパーでお届けします。最新情報は、ソーシャルメディアのアカウントかRSSでフォローしてください。また、私の個人アカウントもぜひフォローをお願いします!