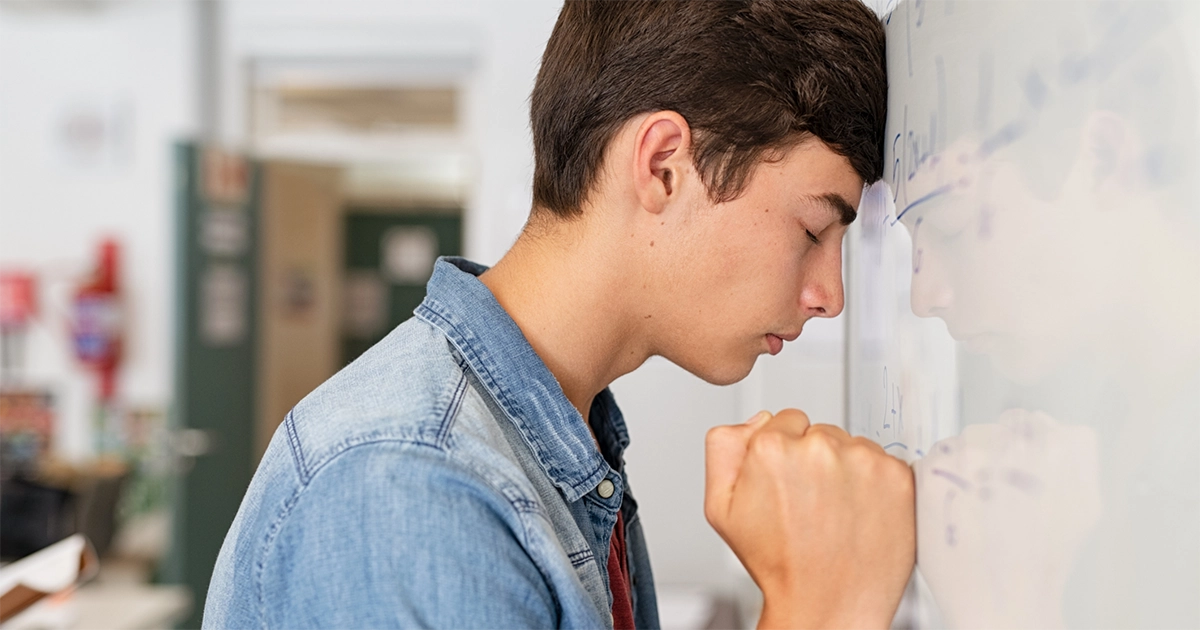AIや顔認識、ブロックチェーンとNFT…転売対策の技術と可能性

転売が、金額の高騰だけではない社会問題であるにもかかわらず、さまざまな問題が複雑に絡むことで解決を難しくしています。
しかし、持続可能なエコシステムを構築するには、ネガティブなリスクを抑制し、正規のビジネスを促進することが不可欠です。そのための技術的な解決策があるのでは?今回は、チケットや商品の転売・改ざん防止に、使われている・期待されるテクノロジーにスポットを当ててみましょう。
ブロックチェーンによるNFTチケット
スマートフォンとモバイルアプリの普及もあり、QRコードやバーコードのデジタルチケットが広く普及しています。会員登録で購入者の情報とリンクされ、正規の購入者であることを証明しやすくなっています。取引履歴を追跡できるトレーサビリティーが確保されているので、転売行為を監視しやすいメリットもあります。イベント当日に本人確認する際にも役立ち、不正コピーや偽造のリスクが低いのも安心です。
次世代のチケットとして注目されているのが、NFTチケットです。これは、情報交換の台帳である、ブロックチェーン技術をベースにした仕組みです。
コーチェラは、毎年4月にカリフォルニアで開催される、アメリカ最大の音楽とアートの祭典です。今年は、YOASOBIや初音ミク、新しい学校のリーダーズなども参加し、過去にはPerfumeもラインナップに名を連ねた人気イベントです。そのコーチェラが、NFT(非代替性トークン)マーケットプレイスのOpenSeaと提携しました。
複製可能なデジタルデータの真贋性を担保するNFTは、主にアート関係で先進的に導入されてきました。ただ、アートそのものより、仮想通貨と連動し、転売した価格の高騰が話題になることがメインでした(この点では、次世代型転売を焚きつける面も)。
NFTチケットは、不当転売や偽造防止だけでなく、正規購入者が柔軟に権利を譲渡できる仕組みを構築できます。さらに、購入者を特別な限定イベントに招待したり、イベント終了後もチケットを永続保存・販売することも可能です。また、転売の透明性を確保し自社でコントロールすることで、アーティストにもインセンティブが割り当てられるメリットもあります。
日本でも、NFTでチケットを取り扱うプラットフォームが2022年に初登場しました。今後、このニーズは拡がっていくと期待されます。
CRM+AIで高度化するマーケティング
デジタルマーケティングにもAI導入が拡がり、CRM(顧客関係管理)によるデータ分析とインサイトの提供はさらに進むでしょう。
既存ユーザーであれば、ファンクラブの加入期間やチケット購入・参加回数、グッズの購入履歴、個人の嗜好などが把握されます。コミュニティーへの貢献度や影響力に応じた、よりパーソナライズされたコンテンツやオファーを提供すれば、顧客満足度がさらに高まります。もちろん、これは転売防止にも有効。
新規ユーザーの獲得に対しても、ソーシャルメディア上のファンの声を分析し、トレンドやニーズを把握して、マーケティング戦略を自動で最適化できます。投稿へのエンゲージメントや、イベントの人気度、競合調査などを総合的に分析。高度なアルゴリズムや機械学習を用いたITシステムで、膨大なビッグデータが瞬時に処理されます。
需給バランスを調整して、収益を最大化させるダイナミックプライシングは、転売の抑止効果も考えられます。また、地域ごとの需要を予測してオーバーツーリズムを防いだり、地域別の販売戦略を立案できます。ただ、熱心なファンはそれでも、分散された日程や、行ける範囲の場所はすべてに参加したいもの。例えば、購入枚数と入場回数の両方を制限し、本人確認を厳格にするような手段の是非が判断されるでしょう。
より厳格な登録管理システム
購入者の本人確認は、モバイルの電話番号やクレジットカード番号なども含め、現状でも各種の個人情報で厳密にチェックされています。しかし、それを通過した購入後に転売されているのが実情。
今後は、金融機関などで導入されている3D顔認証や、日本ではマイナンバーとの紐付けも検討される可能性があります。前述のように、NFTはこの点でも期待を集めています。
ただ、本人確認を厳格化するほどコストは増え、個人情報のリスクも集約されます。ハッキングや不正アクセスによってデータ漏洩が発生した場合、プラットフォーマーは顧客の信頼を失うだけでなく、法的な責任を問われます。また、顔認識などに関するプライバシー保護規約が国や地域によって異なる点は、引き続き注意が必要です。
現場オペレーションを省人化
イベントの場合、特定の日時に本人がその場にいることを瞬時に確認できる、現場の運営も重要です。そしてこれもまた、セキュアに管理されるべき情報です。
人手不足がさらに深刻になることを考えると、効率的に本人確認できるシステムを整備する必要があります。ただし、システムの不具合で入場・開演時間が遅れる事例も現実に起きています。監視にはカメラやセンサー、誘導や警備にはロボットが導入される一方、緊急事態の対応など、人でなければならないオペレーションに人材を配置せざるを得ません。
異常なトラフィックの監視
2020年11月に発売されたSONY PlayStation 5では、オンライン購入では大量のBOT(自動化プログラム)が使われました。本体が奪い合いになる一方、ゲームはそれほど売れず、ハードウェアとソフトウェア需給のアンバランスが起きました。
発売日時になった瞬間にBOTが稼働し、トラフィックが集中することで、サーバーがダウンまたはつながり辛くなります。正規会員でも上位のチケットが取れず、差額を払ってでもアップグレードしたい熱烈なファンが、結果として転売マーケットへ流れていきます。
不正行為が発覚したアカウントは、事前の警告なく即追放を明言しているプラットフォーマーもあります。AIで購入履歴や行動パターンを分析することで、不正なユーザーをより正確・迅速に特定可能になる一方、判断ミスによる混乱も起きるでしょう。
決済手段も多様化・多国籍化
国やプラットフォームによっては、国外で発行されたカードやプリペイド式カードは受け付けられません。PayPalに非対応のサービスもあります。
近年では、QRコードによるモバイル決済に対応したサービスも増えています。日本国内では、PayPayやメルペイ、Amazon Pay、Apple Pay、LINE Payなどが主流です。コンビニ決済のニーズも根強い一方、中華圏のインバウンド向けにWeChat Pay、Alipayなどにも対応すれば、管理は煩雑になります。
NFTチケットとセットで、仮想通貨による決済オプションも期待されます。
対策強化のコストをどう最適化するか?
さて、これらが実現すれば、転売や偽造のリスクを低減できる可能性はあります。ただし、ITシステムは常に、コスト、機能、時間のバランス。テクノロジーの進化や自動化の活用、パートナーシップの形成など、総合的に判断することが不可欠です。
コスト負担の増加要因
- 開発・運用コスト:新技術を導入したシステム開発コストが発生します。ブロックチェーンや次世代の認証技術を使うには、初期投資が大きくなる可能性があります。運用に掛かるコストも無視できません。
- セキュリティー:本人確認を厳格にするために取得・照合・保存する情報は、よりセキュアに管理することが求められます。プライバシー規制に沿った透明性も必須。
- 顧客サポート:新たなトラブルや問い合わせが増えることで、顧客サポートの負担も増加すれば、追加リソースが必要となります。
コストの軽減策とバランス
- 長期的な利益:本人確認の厳格化は、転売や偽造チケットのリスクを低減し、ステークホルダーの収益を保護することにつながります。長期的には、コスト以上の利益をもたらします。
- ファンの信頼向上:ファンが安心してチケットを購入できれば、正規の販売ルートが促進され、全体的な市場の健全性が向上します。
- 自動化の活用:各種の操作を自動化し効率的に処理できれば、運用コストを大幅に削減できます。
- デジタルIDの導入:ブロックチェーンなど、デジタルIDを活用して本人確認のプロセスを簡素化する手法も有効です。セキュリティーを高めつつ、コストの効率アップ、新たな付加価値が実現します。
- パートナーシップの形成:各種サービスとAPIで提携すれば、コストを分散させながら、スケーラブルなシステムを迅速で開発可能です。
転売や情報漏洩のリスク防止、マーケティング目的とはいえ、システムに掛けられるコストには限界があります。また、認証や規制を強化し過ぎると、自由な経済活動・表現活動の阻害にもなるため、バランスが非常に難しいところです。
さて、転売対策として、私たち消費者個人が少しでもできること・すべきことはあるでしょうか?そしてそこには、転売に直接関係なくても、企業や組織のブランドとしての日頃の活動にヒントになることは、何かないでしょうか?連載の最後に考えてみます。