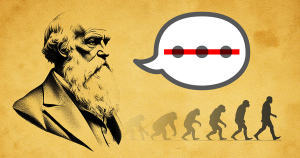適者生存の誤解に騙されず、アジャイルの本質を正しく理解しよう!

以前の記事で、生物学者のC.ダーウィンが『進化論』で唱えたという「適者生存」の言説は、事実ではないことについて解説しました。また、ビジネスの文脈で語られるように曲解された背景にも触れました。
「変化すれば生き残れる」「柔軟な者だけが勝つ」「競争原理とは自然の法則であり、弱者が淘汰されることは自然の摂理」といったあまりにも乱暴な教訓は、進化論の本質から外れた一面的な解釈です。
この誤解を解くことは、俊敏で柔軟なプロセスであるアジャイルの正しい理解にも通じているのではないでしょうか?今回の記事では、その点を俯瞰してみましょう。
誤解される「適者生存」と『進化は進歩ではない』理由
前回の記事で紹介した本で、著者の千葉教授はこう言い切っています。
生物進化は一定方向への変化を意味しない。目的も目標も、一切ないのだ。
また、ダーウィンが説いた『進化は進歩ではない』ということや、「適者」が何を意味するのかについても、丁寧に解説されていました。これらは、アジャイルを理解する上でヒントになりそうです。
進化は進歩ではない
- 生物の種は、共通祖先から分化変遷してきたものであり、常に変化する
- 生物の種は、形のギャップで恣意的に区分される変異のグループに過ぎない
- 変化を引き起こした主要なプロセスは、自然選択である
「適者」の本来の意味
- 「適者(fittest)」とは、「最も強い者」ではなく「環境に最も適応した者」のこと
- 「フィットネス(fitness)」も、「筋力」ではなく「環境への適応度」のこと
- 変化に対応する能力も含まれるが、常に変化することが生存戦略とは限らない
変化への適応で失敗・成功した企業例
言説の誤解はそれとして、時代やマーケットの変化に適応できなかった・できた著名な企業の事例を見てみましょう。市場や顧客ニーズの変化に適応できなかった企業は、淘汰されてきました。一方、プロダクトやサービスを変化させた企業は、生存確率のチャンスを上げただけでなく、イノベーションにチャレンジしたことで大きなアドバンテージを得ることができました。
適応できなかった企業
Kodak
- デジタルカメラの技術を持っていたにもかかわらず、フィルム事業に固執
- 適応のタイミングを誤り、市場から撤退
- 事業シフトに成功した富士フイルムとは対照的
Nokia
- スマートフォン市場への移行が遅れ、AppleやSamsungに敗北
- 変化の兆しに対応できず、市場シェアを失う
- マイクロソフトに事業を売却し、通信機器メーカーとして再出発
適応できた企業
Amazon
- オンライン書店から、巨大ECプラットフォームへと拡張
- クラウド(AWS)やAI(Alexa)、宇宙産業など、新たな市場へ進出
- GAFAMの一角として、世界的な影響力が問われるレベルに
Netflix
- DVDレンタル事業から、ストリーミングサービスへ移行
- 顧客データを活用し、AIによるレコメンドシステムを強化
- 制作から配給、賞まで、映画業界を大きく変革させる存在に
そもそも「アジャイル」とは?
ここで、改めてアジャイルの基本についておさらいしてみましょう。
アジャイル(俊敏さ)とは、変化に柔軟に対応し、迅速な価値提供を目指す思想です。ITに限った姿勢ではなく、ビジネス全般にも応用されています。2001年に発表された「アジャイル・マニフェスト」では、以下の価値観が提示されています。
この中で特に重要なのが、「計画に従うよりも変化への対応を重視する」考え方です。環境への適応を可能にする仕組みが重要であり、常に変化し続けることや、無計画な変化が生存戦略とは限らないという点は、前述の「適者」本来の意味に通じています。
- プロセスやツールよりも個人との対話
- 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェア
- 契約交渉よりも顧客との協力
- 計画に従うよりも変化への対応
アジャイル開発の主な特徴とメリット
アジャイルは、ソフトウェア開発の方法論として広まりました。従来のウォーターフォール開発が計画重視なのに対し、アジャイル開発は反復的に変化するインクリメンタルなアプローチを採用しています。
迅速・高速な価値提供
- 小さな単位による、反復的な開発(イテレーション)
- 開発サイクルが短いため、機能を迅速にリリースできる
変化への柔軟な対応
- 要件の変更や新たな市場ニーズにも、迅速に対応可能
- ユーザーからの早期・定期フィードバックに対し、細かく改善
開発リスクの低減
- 小さな単位で開発するため、大規模な失敗を避けられる
- 継続的なテストと高速なデリバリーにより、品質を確保
チームのエンゲージメント向上
- 自己組織化されたチームが主体的に取り組むモチベーション
- 透明性のあるプロセスによって育まれる信頼感・一体感
アジャイル開発導入のポイント
アジャイルは単なる変化のための変化ではなく、その本質は「環境への適応を可能にする仕組み」にあります。一般企業にとっても、IT業務のアウトソース先であるSIerにもメリットがありますが、未だに誤解されていることも少なくありません。
では、企業がシステム開発に導入するには、どのようなアプローチが必要でしょうか?組織にとっては、資本や人材、時間などのリソースが限られている以上、プロジェクトを進める上で、現実的な妥協点を探るのは必須です。しかし、変化の過程では、何がゴールや正解なのかKPIでハッキリと設定するのは困難です。目的や方向がはっきりとは定まらない中でも、変化に迅速に順応していくには、トライ&エラーを頻繁に繰り返し、フィードバックしていくしかありません。
これは、生物と同様に一朝一夕には変わるものではありません。トップレベルの意識改革から、組織カルチャーの育成、チーム体制作りが不可欠です。
カルチャーの醸成
前述のようなアジャイルという価値観を組織全体で共有し、受け入れる文化を築く。
適切なツールの選定
開発効率を高めるプロジェクト管理ツールを活用し、タスクの可視化と進捗管理を実施。
継続的な改善
スプリントごとに振り返り、開発プロセスの改善点を見つけて改善を続ける。
適切なフレームワークの活用
スクラムやカンバン、XP(エクストリーム・プログラミング)などのフレームワークを活用。
アジャイルの誤解以上の影響があるTESCREAL
ダーウィンは、「最も強い者が生き残る」という乱暴な「適者生存」を主張していたわけではありませんでした。正しい解釈を踏まえて、変化に迅速に対応できるアジリティー(俊敏性)について考えると、アジャイルの本質が見えてきます。
その一方で近年では、倫理や人権、民主主義よりもテクノロジーの進化を重視する考え方が、一定の支持を集めています。これは、適者生存の誤解以上のリスクを孕んでいます。これらの思想についても、注意深く関心を向け続けておく必要があります。
BANIという、先行きが予測不可能な現代を生きる私たちにとって、どのような変化に対しても、柔軟かつ迅速に適応できる仕組みの構築が急務です。固定観念に囚われない、自由な思考で物事を捉えることが求められています。
そのためには、変化そのものではなく、適応の仕組みとしてのアジャイルを正しく理解し、実践していくことが不可欠。変化を恐れるのではなく、適応する力を養うことで、継続的な成長を遂げていきましょう。